 |
Sailing Rolling
伊東忍 with マーク・ソスキン
ゲイリー・キング , ダン・ゴットリーブ
トム・ハレル , ディック・オーツ
マイラ・カセールス , 鈴木良雄
CROWN RECORDS/PAS-1009
(1991) |
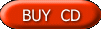 |
|
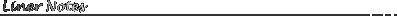
その演奏と共に伊東 忍の人柄は非常に温かみ溢れるものだ。マンハッタンに住み始めて15年目を迎えようとしている彼は、西21ストリートにある小じんまりとしたアパートで自己の音楽を追求している。生き馬の目を抜く競争社会のアメリカ、しかもそのもっとも過酷なレースが行われているニューヨークにあって、伊東 忍はまさに淡々とした風情で目指す音楽を追い求めてきた。その最初の成果がここにある。おそらくこの作品を現在耳にしている殆どの方が、彼の演奏を聴くのはこれが始めてのことだろう。驚くのはニューヨークに住むギタリストにもかかわらず、彼のサウンドが非常にウエストコースト的というかほのぼのしたものがあることだ。それは伊東が湘南に生まれたこととも関係しているのかもしれない。<どうなんでしょうね。別にそういうことを意識はしなかったけれど、そう聞えるかもしれませんね。30になった頃に考えたことがあったんですよ。どんな音楽をやってもいいんだけれど、その向こうにやっぱり空とか海とかを自分はもとめているんじゃないかな、ってね>。妙な気もするが、彼の場合ニューヨークに住んでいながら、いい意味でこの街に毒されていない部分がある。それは勿論音楽についてだけではなく、その人柄というか、大きく出れば彼の人生感についてまでも言えるようだ。<僕の音楽はむしろカリフォルニア的かもしれない。でも10年ぐらい前にT.M.スティーブンス(b)やカイル ヒックス(Dr)とバンドを作っていた時は、ギンギンにフュージョンをやっていたんですよ>。しかしそうした音楽を聴かせるクラブが当時のニューヨークには殆ど無かった。そんなこともあって伊東は次第に音楽感を変えていったという。<もっと自分に素直になろう、というのが一番の理由です。やはり最初はどこか無理をしていた。とにかくニューヨークに来て、エーイ何かやってやろう、という気持ちだったのですね>。
オープニングの<セイリングローリング>はまさしく海の薫りを響かせた心地よいサウンドが全編を覆っている。そしてこのサウンドはアルバム全体を通しても共通するものだ。実はこの曲をかいた鈴木良雄が今回のプロデューサーでもある。ご存知の通り鈴木は日本を代表するベーシストとして、70年代から80年代に書け10年以上に渡ってニューヨークに住みながら世界の檜舞台で活躍してきた人だ。その彼が今回伊東のために初のプロデュースを買って出た。<前からチンさん(鈴木のニックネーム)に曲を聴いてもらったりして、そろそろレコード作ったら、なんていうアドバイスも受けていました。曲もずいぶんたまってきたし、チンさんにデモテープみたいなものをおくったんです>。それが今回のレコーディングに繋がったというわけだ。これまで自分から売りこみなんかしたことなかった、と語る伊東だが、機は十分に熟していた。<まあそれからずいぶん大変だったんです。チンさんも凝り性だから、あそこが2小節多いとか、次になるとやっぱりあれはあれでいい、とかね。国際電話で何度も何度も打ち合わせですよ>。しかし事前に検討を十分にしたことが、結局はレコーディングをスムースに進行させる要因になったと伊東は振り返る。<チンさんと知り合ったのは、僕がニューヨークにきてからなんです。たまたまチンさんと同じアパートに住んでいた友人が紹介してくれたんですね。あまり一緒に仕事をしたことはないんですけど、ああいう暖い人ですからずいぶんとお世話になりました>。
1951年生まれの伊東忍は、この世代の多くの少年がそうだったように、中学時代にベンチャーズの洗礼を受けている。父親がギターを弾いたこともあって、まず、最初に彼は父親からギターの手ほどきを受けたという。ジャズに興味をもったのは高校の頃で、きっかけはウエス モンゴメリーを聴いたことだった。東海大学にはいって本格的にジャズギターを始め、大学3年になるとすでにプロとしての活動をスタートしている。プロになってからの伊東にとって一番の勉強になったのは、六本木にあった「J&B」で木村好子のグループに入ったことだ。<77年だったと思うんですけど、ちょうど六本木の「ピットイン」がオープンしましてね。近くには「ミスティー」なんかもあったし。「J&B」は遅くまでやっていたんで、仕事を終えたミュージシャンがあそびにくるんです>。そこで向井滋春、峰厚介、土岐英史、中村誠一、植松孝夫、山本剛、といった人たちとしょっ中ジャムセッションをしていたことが、彼にとっては大いに勉強になったというわけだ。
話は前後するが、75年に伊東は初めてアメリカの土を踏んでいる。<その時はロスに行ったんです。いいギターでも買おうかな、っていうつもりだったんですが、偶然秋吉敏子さんと知り合いましてね。彼女のビッグバンドのお手伝いなんかしていたんですよ。シェリーマンのドラムスを運んだり、譜面配ったりね>。その彼女が、ジャズをやるなら絶対ニューヨークに行くべき、とアドバイスしたことが今日に繋がっている。半年間ロスに滞在した伊東は一旦日本に戻り、次なるニューヨーク行きの準備に取りかかる。2年後の77年にニューヨークについた時、彼の中に確たる計画はなかった。<とにかく知り合いなんて一人もいませんでした。スイングジャーナルに書いてあったギタリストの川崎 僚さんの住所を訪ねたら引っ越したあとだったり、という程度でしたからね>。最初に伊東がニューヨークで演奏を始めたのは、ブルックリンにあったレジーワークマンの主催するオーケストラでのことだ。それから徐々にミュージシャンと知り合い色々なセッションに顔を出すようになっていく。やがて彼はニューヨークの日本人ミュージシャンでもっとも成功した一人、中村照夫率いるライジングサンに参加する。<突然照夫さんから電話かかってきましてね。譜面読めるか、って聞かれまして、あまり自信は無かったんですけど、ええって返事したら、行きのバスで突然譜面渡されて、リハーサルも無しで本番ですよ。でもすごい体験でした。あのころはファンクが流行っていましてね。音が渦を巻くっていう体験を初めてしました>。とにかくニューヨークについてしばらくは、伊東もいわゆる当時のフュージョンを主として演奏していたようだ。<アルバムに収めているのはここ5年ぐらいの間に書き溜めていた曲なんですね。スタンダードの「マイ ワンアンドオンリー ラブ」はハーモ二クスの練習をしていた時に、ちょっと何とかなるかなと思ってレパートリーにしたんです。好きな曲ですしね。それから「ウエストサイド ストーリー」の<サムホエアー>。これも好きな曲だったんですね。ほのぼのとした明るさに満ちた演奏、、、それがこの作品の大きな特徴である。<でもライブはもう少し賑やかなんですよ。ニューヨークのお客さんはもっと刺激を求めますからね。このアルバムの中のサウンドというものは、ある意味でレコーディングのためのものかもしれません>。メンバーもそのためにプロデューサーの鈴木と選んだという。<ゲイリーキングはボブジェームスの演奏で1−2曲すごく気に入っているのがあるんですね。でその演奏を聴いていて、どんな人だろうと想像していたんです。スタジオ系の人だし、まずチンさんはしらないだろうとおもったんですが、ゲイリーなんてどうだろう、って言ったらチンさんも実はエレクトリックベースで一番好きな人だって言うじゃないですか。それでだめ元で電話したらこれがすんなりOKになったんです>。<ドラムスが中々きまらなかったですね。色々かんがえたんですが、最初はバディーウイリアムスとかね。結局ダンゴットリーブにしたんですけど、彼で良かったと思っています。ゲイリーとは合ったみたいで、コンビネーションは良かったとおもいます。シンバルなんかすごく綺麗に叩きますし、僕の音楽にはその繊細さが必要だったと感じています>。たしかにそうだ。あまりここでヘビーなドラムスが来ても、演奏自体はアンバランスなものになっていたかもしれない。<キーボードも一杯候補がいたんですよ。例えばマークコーエンとかジムベアードとかね。チンさんはジムを色々な人から推薦されていたみたいだけど、最終的にマークソスキンにしました。彼はエレクトリックもアコースティックも上手く弾ける人だし、今回のようなセッションには最適だと思っています>。<トランペッターは最初ブラジル出身のクラウディオ ロディッティーにしようかなともおもったんですが、最終的にトムハレルになりました。トムはチンさんとも昔よくやっていたし、そういうのもあってやり易いんじゃないかと。彼は本当に素晴らしいトランペットを吹いてくれましたね。あのラインはやはりトムにしかできない。そういう
感じで僕のアルバムに参加してくれました>。このところコンテンポラリーレーベルから快作を連発しているトムハレルの参加も本作を魅力的なものとする大きな要素に違いない。<ディックオーツはチンさんの好きなサックス奏者で、一度きいてみろよ、って言われて初めて聴いたんですが、いい音をしていますね。それで僕もすぐ好きになってしまいました。トムとディックのコンビネーションというのもすごく上手くいってるなと僕は思っているんですけど>。ピアニストのゲイリーダイアルとダイアル&オーツで活躍中のディックオーツは、現在毎週月曜日に「ビレッジバンガード」に出演している“ザ バンガーズ”(かつてのメルルイス ジャズオーケストラ)で重要なソロイストとしても活躍中だ。<パーカッションのマイラ カザルスは、以前「パッツ」で演奏していた時、オーナーから紹介されたんですね。現在はアンジェラ ボフィルのバンドにいるのかな。女性なのに力強いし、ライブやらせるとショウアップしてすごいんですが、レコーディングではそれが出来なかったのがちょっと可哀想でした>。という具合だが、これ以上作品について紹介する必要はないだろう。伊東忍というギタリストがいまぼくたちの前で大きく羽ばたこうとしている。ニューヨークの厳しいミュージックシーンの中で熟成させてきた彼の音楽は、奇妙なほどにニューヨーク的ではないかもしれない。しかしそれは僕達が勝手なイメージの中でニューヨークの音楽はこうだ、と決め付けているからだ。どんなにカリフォルニアの青い空を彼の音楽から感じたとしても、それは伊東忍がニューヨークの喧騒溢れる猥雑な街のなかで求め続けてきたサウンドの他ならない。そこに彼の純粋さ、あるいは己の完成に素直な形で対峙している姿が見てとれる。ぼくはいまそんな伊東忍の音楽が好きでたまらない。
小川 隆夫

|










